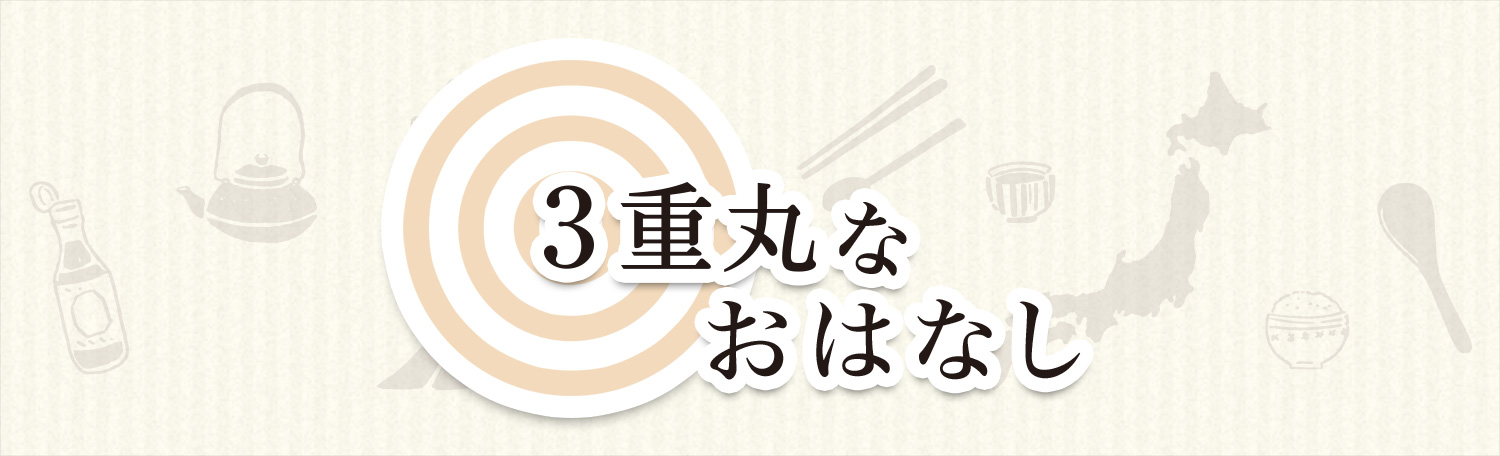
体に効く食薬ごはん 8月「茗荷(みょうが)」
2024年8月30日(金)
特に暑い季節には欠かせないですね。
少し秋の気配がするけれど、まだまだ夏の暑さが残っているこの時期は、夏後の疲労が出やすい頃です。
さわやかな辛みを食事に取り入れて、夏疲労や秋あたりをケアしましょう。

効果・効能
茗荷の香り成分には発汗作用があるので血行を良くします。また消化をよくする効能も期待できます。
クーラーや冷たい飲食で、体が冷えやすい夏には特にお勧めの野菜。
独特の香りや心地よい食感で、気の巡りも良くなり、リフレッシュします。
アントシアニンやカリウムも含まれる為、むくみやかぜ予防にも有効です。
使い方
色も美しいので、何かとお料理のアクセントになりますね。3〜4月頃が旬の茗荷竹は若い頃の茎で、天麩羅に美味しいですよ。
7月頃の早茗荷(わせみょうが)は比較的小ぶりで、8月に入ると赤く丸みを帯びて秋茗荷となります。
冷奴・そうめん・刺身のツマなどに添えると清々しさが演出できます。
9月に入るとさらに瑞々しく香りの良い秋茗荷が出回ります。 今の時期出回る秋茗荷は、夏の茗荷と比べると白っぽい色味が特徴です。
茗荷はその刻み方で香りや食感の表情が大きく変わります。
刺身のツマにする時は、横薄切りにして水に5分ほどさらします。
繊維を断ち切ると香りが立ちやすくなるのです。
また、縦に切るとしゃきしゃきとした歯ざわりが楽しめます。
生のままサラダや和え物に加えていただくと、食感が引き立ちます。
【ぬか漬け】
立秋を過ぎましたが、まだまだ残暑が残ります。
疲労を感じやすいこんな時こそ、ぬか漬けもお勧め。
汗をかくので、ぬか漬けの塩分が美味しく感じます。
酸味も心地よく、よく冷えた茗荷やキュウリの漬物などは格別ですね。
腸内の免疫力(体の6、7割は腸が作る)をupする食材として、日本の伝統食のぬか漬けは素晴らしく、胃酸にも強いと言われている植物性乳酸菌がたっぷり。
含まれるギャバには脳の興奮を抑える効果が期待でき、夕食時にいただくと安眠出来ると言われています。
ギャバは発芽玄米・納豆・トマト・きのこなどにも多く含まれています。合わせて相乗効果を担ってもよいですね。
発酵が進んで塩気や酸味が出た漬物は、旨味も増しています。
漬物をお椀に入れ、冷たい昆布だしと調味料少々で味を整えると、簡単に涼を呼ぶ美味しい汁物になり、元気が回復します。

【茗荷の天ぷら】
秋茗荷の小ぶりのサイズを目にしたら、
早々天つゆや香り塩を仕込みます。
薄く衣をつけた揚げたての茗荷を一口で頬張ると、
香りが鼻を抜け、心地よい食感が何とも粋。
茗荷の天ぷらは初秋の醍醐味ですね。
暑い日ならそうめんの付け合せにも最適です。

【茗荷の甘酢漬け】
まだ暑いので甘酢もいいですね。
甘みを少し加えた酸味は津液を潤し、
香りを含めた効能が疲労回復を潤す手助けをします。
縦に薄切りにした茗荷5,6個分をさっと塩茹でする。
水気をしっかり切り、
熱いうちに甘酢(米酢1/2カップ、きび砂糖大さじ2、塩少々)に
漬けると、鮮やかな紅色に発色します。
なにかと重宝する茗荷の甘酢漬け。
これを刻んでご飯に混ぜれば即席のお寿司がすぐに作れます。
茗荷を漬けた甘酢に焼き鮭やちりめんじゃこをくぐらせてご飯に混ぜると、さっぱりとした旨味で、食欲がない日にも箸が進みますし、和え麺などにも良いものです。
甘酢漬けに、ローリエやスパイスを加えれば洋風の即席ピクルスにもなります。色々なレシピを楽しんで下さい。
※津液:体の水液の総称(唾液・胃液・涙・汗など)
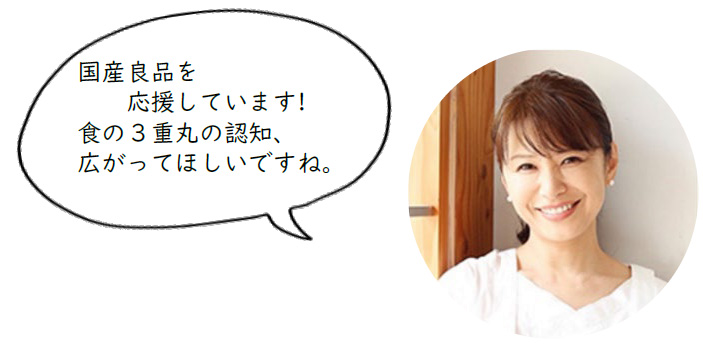
料理家。調理師、国際中医薬膳師、国際中医師
NHKカルチャー薬膳講師
旬の食材の効能と素材の味を生かした
シンプルな料理に定評がある。
醗酵食レシピの開発はライフワーク、薬膳に造詣が深い。
レモン塩、乳酸キャベツブームなどの
火付け役としても知られています。
NHK「きょうの料理」「あさイチ」「趣味どきっ!」「ライフ」などの料理番組他、企業CM、商品開発、雑誌、カタログ、イベント、書籍、発酵レストランなどのプロデュースを手掛ける。
link:【食薬ごはん】
Instagram:【yumiko_izawa(井澤由美子)】

